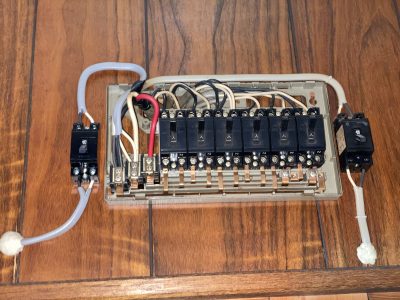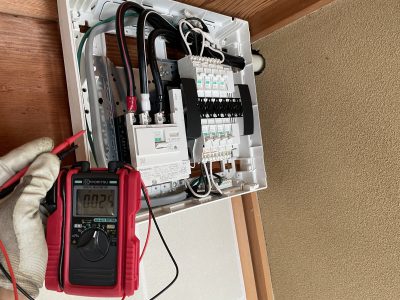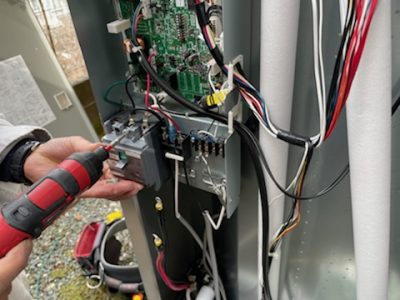はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!
今回は、一般住宅における、引込、幹線廻りの改修工事の様子を
お伝えしようと思います(‘ω’)

右のお宅が現場ですが、おおまかな内容としては
お
客様がお風呂の蛇口を触ると
【ビリっ】と感じるということで、関西電力に見に来てもらった
ところ、
屋外の電力メーターから分電盤までの幹線の間で漏電している
ということで、兵電工組合をとおして弊社に連絡があり、
とりあえず見に来てほしいということでした(‘◇’)ゞ

カーポートの奥に電力メーターがありましたが、
売電用のメーターもついておりました(‘ω’)
聞くと、太陽光はもう10年経過して使っていないので、使っていない
とのことで、関西電力にきてもらい、その売電用計器ボックスの中は
メーターは外してあり、幹線をつないでいるBOXとして置いている
だけのようです((+_+))
ただ、パワコンや接続箱はまだ電源ランプは光っていて、作動している、
もしくは逆潮流の電気がまわってきて、漏電しているなど、いろいろ
考えられる要素がありました(; ・`д・´)

お隣様との間を進んでいくと、二つ目の窓が洗面所で
この洗面所内に分電盤があります(*’ω’*)

さらに奥までいくと、上部に、パワコン関係があります(; ・`д・´)
そして、家の角を曲がったところに
エコキュートが設置してありました(‘ω’)ノ

たしかに、パワコン横の小さな接続箱は電源ランプがついているので、
直流のブレーカーは生きたままのようですね((+_+))
家庭用の太陽光って売電期間の10年が過ぎたら、施工業者とかも
ほったらかしで、お客様もどうしたらいいのか、
わからないのでしょうね((+_+))


左側の計BOX下のP.BOXで、奥のパワコン手前のウオルBOXまで
幹線を分岐して送っているもの、
そして左の計器BOX内で洗面所分電盤へいっている幹線が
貫通して壁の中に入っていて、
それらがジョイントしてあります(‘ω’)ノ
、、とにかくグチャグチャでわかりにくいですね((+_+))
お客様は不安に思って、水道屋さんに、蛇口やエコキュートも
診てもらったようなのですが、設備側には問題なかったとのことで
屋外の計器BOXから屋内配線されて、洗面所へいっている幹線を
怪しむしかなく、そこを取替することになりました(; ・`д・´)
お客様のご了承を経て、既存の幹線は切り離して、新たに外壁まわり
より幹線を配管・配線する施工に致します(‘ω’)ノ

というわけで、右の計器BOXから左の2番目の窓あたりまでを
まず配管してしまいます(‘ω’)ノ

洗面所の部屋隅を狙って貫通穴をあけます(‘ω’)

洗面所内の角から、分電盤までは露出でプラスチックモールで
配管、配線させてもらいます(‘ω’)ノ

養生したのちに、貫通穴をあけてしまいます( `ー´)ノ

プルボックスなどつけるか迷いましたが、できるだけ安く、
見た目もコンパクトに納めるべく、PFD28を直接壁内まで
取り込む最小限の穴をあけます(‘ω’)

貫通穴もあいたので、モールも配管していまします(‘ω’)

これで、室内の入線までの準備完了です(‘◇’)ゞ

さて、屋外の配管ですが、いける直線はVE28で配管するので、
異種管コネクタがつく分、炙って、配管をまげておきます(‘ω’)

配管支持材サドルエースを取付ていきます(‘ω’)

そして、作り物をしていたVF28をとめていきます(‘ω’)

PFD28に変換し、先ほど開けた貫通穴へこんなイメージで
とりこみます(‘ω’)

途中、関西電力様が、メーターの取外しに来られました。
一応、メーター接続や取替は関電の持ち物なので触ってはいけません(‘ω’)
(こちら側で勝手に取り外したり、仮につないだり結構しますが、、)
施工後、再びメーターへの接続は関電がするのですが、
何時に終わるかわからないし、また関電がくるまで停電しっぱなしもお客様
への負担になるので、
施工後のメーター接続はこちら側がして電圧や絶縁のチェックもすることで
合意しました(‘ω’)


関電が作業している間、新しく、CVT14sqを入線しておきます(‘ω’)



おおまかな入線は完了です(‘◇’)ゞ

洗面所内にも線がとりこまれましたので、
モールへいれていきます(‘ω’)ノ


貫通穴のパテ埋めはきっちり施して、納めます(‘ω’)

分電盤への接続も済ませて、屋内は完了です(‘◇’)ゞ


あとはメーター廻りですが、
切り離した、前の幹線SV14sq-3Cをメガチェックしてみますが、
絶縁はそんなに悪くはありませんでした(; ・`д・´)
、、ということは、漏電の原因は他にもあるということです(; ・`д・´)
、、とりあえずまず停電中なので、復電するべく作業を進めます(; ・`д・´)

計器BOXは一つ外して、代わりにウオルBOXを取付、
そこで、奥へいっているパワコン手前のウオルBOXに幹線が
分岐しているのですが、一番上側に主幹漏電ブレーカーをつけておきます(‘ω’)
奥のウオルBOXでは、前の太陽光、IHクッキングヒーター、エコキュートがそれぞれブレーカー
がついていました(; ・`д・´)
ただ、屋外の上のほうに、1次側から分岐した回路がプラスチックの箱
の中で設置しているのは、どうも危険でリスクが高いので、
メーターすぐ横に、主幹75Aを設置させてもらうようにしました(; ・`д・´)

まずモジャモジャ達を取っ払ってしまいます(; ・`д・´)

新しくウオルBOXを取付し

主幹ELB75Aをつけます(‘◇’)ゞ
※コロナの影響でブレーカーの納品が遅く、しばらく倉庫に転がっていた
仮のELB100Aをつけますが、後日交換します(; ・`д・´)

1次側の配線や、分岐回路なども配線していきます(; ・`д・´)
またモジャモジャなってきましたね(; ・`д・´)
計器BOXは耐候性の新しいものに交換させていただきました(; ・`д・´)



接続完了で、やや、すっきりできたかなと(; ・`д・´)

昔はグレーの計器BOXしかなかったのですが、
外壁に合わせて、ベージュや黒など今は色を選べるので
できるだけ景観に溶け込むようにします(‘ω’)

さて、奥のパワコン手前のウオルBOXですが、
左から太陽光ブレーカー、エコキュート、IHとブレーカーが並んでいるのですが、
太陽光ブレーカーの端子を、端子台として電源送りしていた為に
太陽光ブレーカーを外さないで、置いているようですね(; ・`д・´)

少々曇りの日ではありましたが、もし発電して逆潮流が返ってきてたら
電圧が出るのですが、無電圧でした(‘Д’)
念のため、パワコンへの電源送り線は外してテーピングしておきます(‘ω’)
これで、太陽光からの漏電などは関係なくなりました、、。
やっと復電!
ということでIHのブレーカーをオンにし、
エコキュートの主幹40Aをオンにしたら、
【パチっ】と 新たに設置した主幹75Aがトリップし
遮断されました(; ・`д・´)

エコキュートへいっている、外配管、電線などしらべます(; ・`д・´)
電線は絶縁がよくて、問題がない(; ・`д・´)
エコキュート本体も問題はない(; ・`д・´)
エコキュート本体にELB30Aがついているのですが、

とりはずして、絶縁をみてみると、
悪いですね(; ・`д・´)
どうやら、このブレーカーの内部で絶縁破壊を起こして、
赤線と黒線がショート状態になっており、
その漏れた電流が、エコキュートの銅管を伝って、風呂場の蛇口に
流れているので、
蛇口を触ったらビリっとしたというのでも合点がいきます(; ・`д・´)
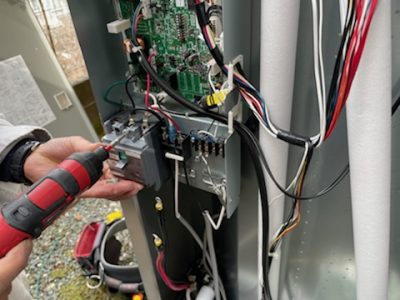
とりあえず、コロナの影響ですぐにブレーカーははいってこないので、
かりに3P30Aをつけておいてしのぎます(; ・`д・´)
後日、ブレーカーがきたら交換します(; ・`д・´)
パワコン横のP,BOXのエコキュート用のブレーカーは漏電ではなく
サーキットの2P40Aだったために、
この漏電でも作動せずに、電流が漏れ続けていてもわからなかった
と考えられますΣ(; ・`д・´)
しかし今回の改修では、1次側分岐した回路の機器や幹線含め全域で
もし、また何か漏電がおきても、今度は主幹の75Aが作動してくれます!
ビリっと怖い思いをされたお家の方は、怖くて、ずっとお風呂を使わずに
銭湯に行っていたようで、
漏電遮断器の適正設置と、もし感電したときのアーシング(接地)
もいかに大事であるかを改めて考えさせられました(; ・`д・´)
家庭用のコンセント100Vでも、関電すると、
条件が悪いと、、○にます(; ・`д・´)
濡れた手で触る、それが左手で、心臓に近いほうで電流が心臓を通っった
場合、42Vで人を○んでしまいます(; ・`д・´)
42(死ニ)ボルトといって、100V以内でも電気ってのは怖いことを
忘れてはいけません(; ・`д・´)