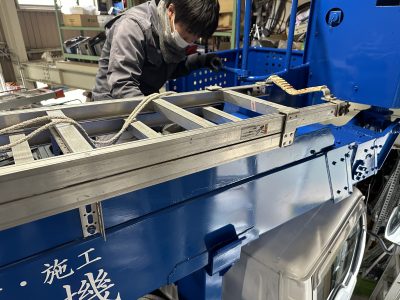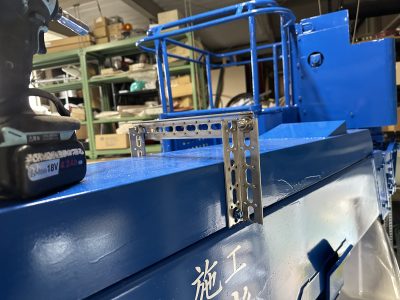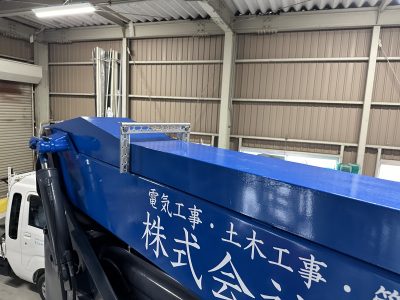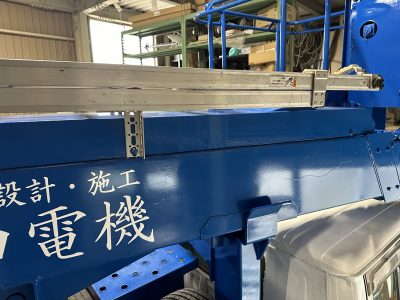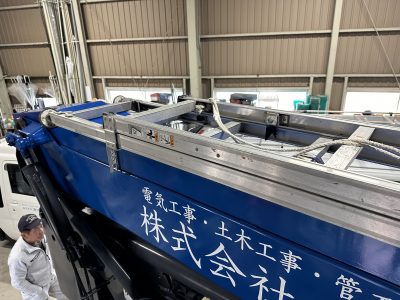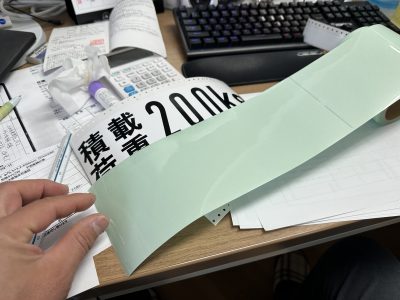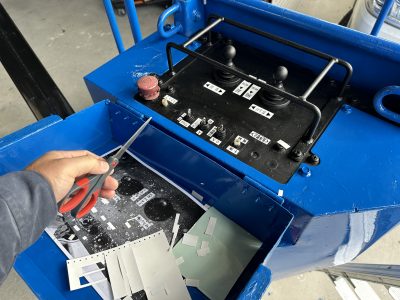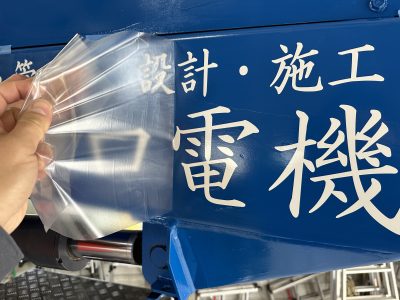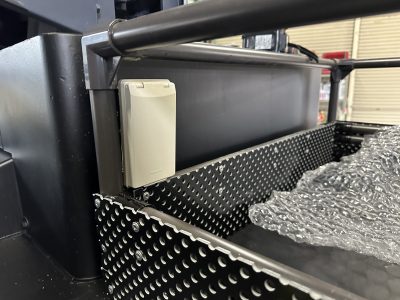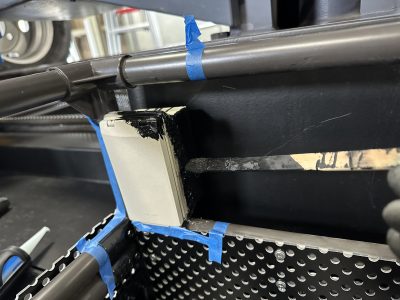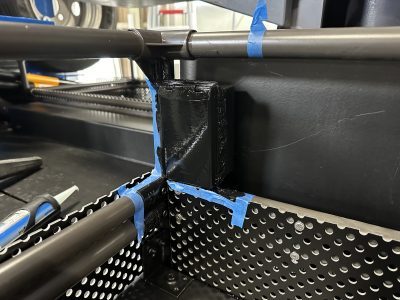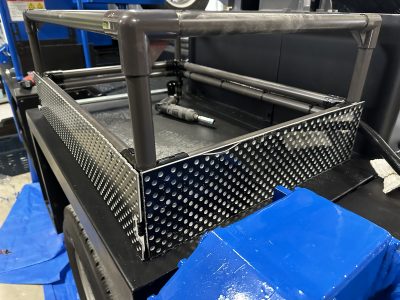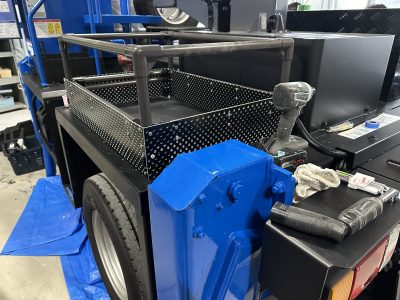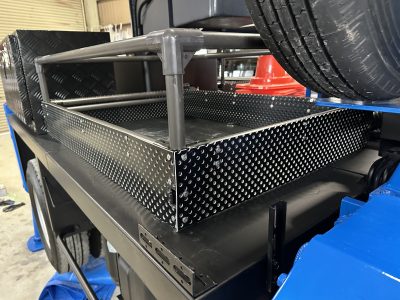はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!
今年の車検で、ハイエースの荷物を全て下したあとに
勢いで、棚など全て取り外してしまいました(‘ω’)ノ
ハイエース荷台スペース解体!
全てを網羅した、『移動倉庫』仕様の以前のハイエース、、
私が一人の時や、何が要るか不安な時などは、
ハイエースに乗っていけば、どんな工事にも対応できる仕様でした、、
ハイエース電気工事仕様!職人棚①(後方スペース)
↑ただ、こういった仕様でのメリットは沢山ありますが、
デメリットもあります(‘ω’)ノ

軽トラなど別車両で、現場に行く時は、
このハイエースから随時、ひつような道具を持ち出す形に
なります(; ・`д・´)
そして、帰社後、また持ち出した道具を返すわけで、、
倉庫の中のハイエースの倉庫から道具や材料を準備する
形になっていることが多く、、
ハイエースに誰かが載って現場にいくと、、
軽トラでほかの現場に行く時、、
あの道具がハイエースに積んであって、それが必要なのに、、
ていうパターンもあるわけです(; ・`д・´)
やはりそういうデメリットも解消したいので
リニューアルを決意(; ・`д・´)!!


色々構想を練り、、
一番何がいいのか、、
行きついた結論は、、
『ほとんど何も積まないようにする』

そう、、倉庫にある 道具や材料を
その都度、軽トラやハイエースに積んでいく
バイキング形式といいますか、、
ハイエースにもほぼ何も積まないようにして、
その都度必要な材料と一緒に道具も積んでいく(‘ω’)ノ
そうすることで、普段はユーティリティスペースを
充分広くとれるわけです(; ・`д・´)!
前までは、運転席と助手席で2人しか乗れない仕様でしたが、
従業員さんが一人増えるので、
3人で遠方の仕事に行く時があった場合に、ハイエース
一台で行きたいというシチュエーションに対応できるように
します(‘ω’)!

よくフロア貼りとかきれいな仕様を見ますが、、
めんどくさがりな私は、、
桐のスノコを買ってきて、、
とりあえずスノコを床面に敷き詰めることにします(; ・`д・´)

地と床板、、それがセットになっているスノコ、、
スノコを並べるだけで床面完成です(; ・`д・´)w

とりあえず後部座席は使えるように、
後部座席より後ろ側に納まるだけのスノコを設置(‘ω’)ノ

並べたスノコ同士も桟木を下に忍ばせてそれぞれが
動かないように固定していく(‘ω’)ノ


そして、フレームパイプで、左後方だけ、
タイヤハウスの廻りを隠すように、出来るだけ省スペース
で棚を組もうと思います(‘ω’)

この棚には、各車両に常備しておく、
例えばテスターやメガ、パテやビニールテープなどの
消耗品などを載せておくためのエリアにします(‘ω’)

出来るだけ出っ張らず、出来るだけ荷台はガラガラにして
置けるようにします(‘ω’)

以前はこんなにアングルで組んだシステムだったのに、、

そして、こんなにも中に収納されてたのに、、

それが、こんなにもスッキリ仕様になっていきます!
、、次回へ続く(; ・`д・´)!