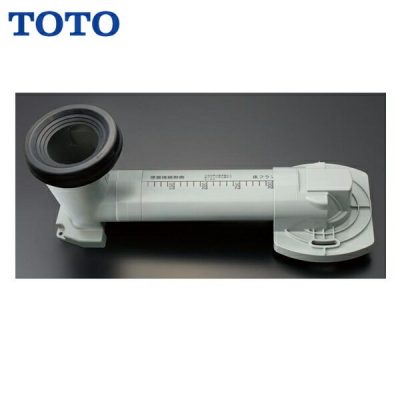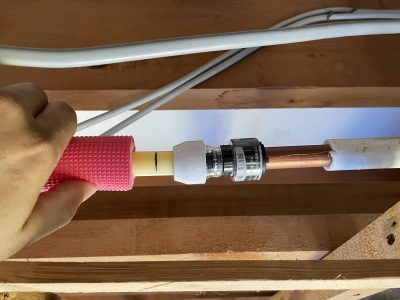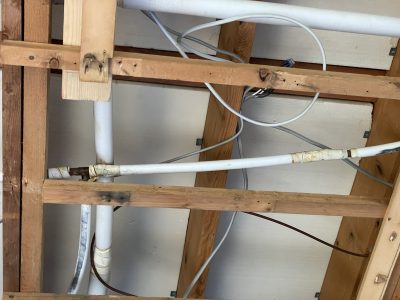はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!
今回は天井に上の階からの水漏れが起きたので
漏水箇所の確認をし、そのあと天井材を張り替えることになった
お宅の紹介です(‘ω’)
こちらのお宅は、以前にも紹介しましたが、2階に水回りがある為、その
下の階に漏水があった場合影響がでてしまうというのを
数年おきに繰り返しております(; ・`д・´)
漏水修繕!
給水装置(蛇口など)自体の古くなると、悪くなりますし、
それをつないでいる『管』もまた老朽化してきます(; ・`д・´)
昔のお湯配管は、銅管でして、
しかもその銅管の品質も今ほどよくありませんでした(; ・`д・´)
厚みが薄いし、すぐへシャがるわけです(; ・`д・´)
なので、ろう付けしたところも、よく溶けて穴がありたりしますし、
エルボやチーズなど継手の接続部も経年劣化で隙間ができて、
そこからちょろちょろ漏れるし、、良いことなしです(; ・`д・´)

今回の水漏れはこの照明器具の横なのですが、
すでに天井材(トラバーチン)は水を吸いすぎてブヨブヨに
なってはがれおちていました(; ・`д・´)

このすぐ横が、以前も紹介したように最初水漏れが確認
できた箇所です(; ・`д・´)

まず、天井材を撤去してしまいたいので、
埋込照明器具などを外します(; ・`д・´)

端子台もビス留めな古いタイプですが、今回この埋込器具は
やめて、新しい露出の器具に更新することになりました(‘ω’)
、、もうネジもぼけていたので、よかった(; ・`д・´)

LED照明も、こういったスクエアの埋込器具は露出器具より
お値段は高いわりに、露出器具よりは照度は落ちます(‘ω’)

手前の天井も、以前に水漏れがあり、天井材はブヨブヨで
水垢で汚かったのですが、
弊社が白いペンキを塗ってしのいでいたものの、
今回一緒に天井をきれいにやり替えていただくことになりました(; ・`д・´)

トラバーチンという天井材なので、石こうボードのジプトンとは
違って、軽いのですが、紙でできているので、
こういった漏水や湿気を吸うと、曲がって変形してしまうのです(; ・`д・´)
ただ、学校やオフィスなどの天井材であるジプトンは、
ビスで留めるため、ビスの穴は見えるわけです(; ・`д・´)

↑これは吸音ボードなので、ジプトンではないですが、
白い軽天ビスが見えているのがわかりますよね(*’ω’*)
こういった感じで、ジプトンはビス跡がみえるので、

虫食いのような柄がついていて、ビスの跡がわかりにくいように
なってます(*’ω’*)
ジプトンのことを『虫食い』という大工さんもいます(*’ω’*)

さて、トラバーチンを外すとこんなかんじです(; ・`д・´)

木地の上に白いパイプが二つ横切っていますが、
これが水道の、水とお湯の配管です(; ・`д・´)

この白いテープで巻いているのが、お湯の銅管の接続箇所(; ・`д・´)
ろう付けだけでは心配だったのかテープ巻いてますが、
水の圧力なんて、テープでは防げませんので
意味は無いです(; ・`д・´)
おそらく、こういった接続箇所が何個もあるので
それらのどこかが漏れていて、てくてくと伝って滴のように
落ちている感じです(; ・`д・´)

ちょうどこのチーズからしずくがぽたぽた落ちてきてます(; ・`д・´)
こういった天井内のコロガシ配管でも、接続部あたりは
配管を吊ったり、どこかに固定しておかないと
つねに配管に重力と水が流れたときに重みで下方向に負荷が
かかるので、接続部に負担がかかるわけですね(; ・`д・´)

外壁面で配管は2階に上がっているのですが、
このあたりでも、3か所くらい接続されていて、
この接続部もあやしいもんです、、(; ・`д・´)
まずこのお湯配管を取替してから、天井材をやり直す方向で
進めていきたいと思います(; ・`д・´)