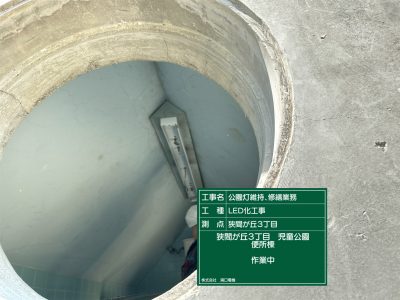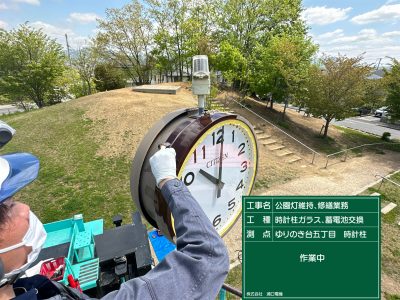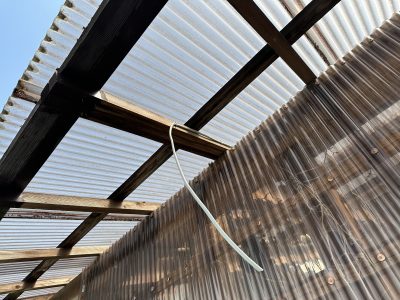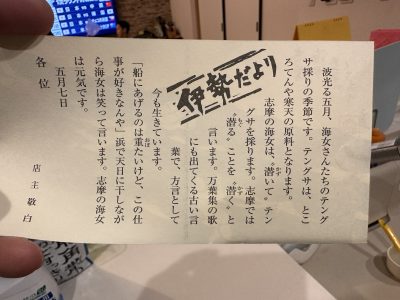はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!
一戸建てを所有されている方で、田舎の方は必見(; ・`д・´)

私の自宅は築6年目で、まだ比較的新しいのですが、
もともと、雑排水の配管勾配があまりとれておらず
緩やかな勾配で、裏庭にある浄化槽につながっています(‘ω’)

右のほうから、洗面、一階トイレ、そして、エコキュートが
設置されている左に浴室があり、二階の便所の排水も、真ん中
あたりで合流してます(‘ω’)
そして、物置の奥にはキッチンがあって、シンクからの排水管
がつながっています(‘ω’)

下水が繋がっていない地域の為、このあたりは
一家に一台、浄化槽がそれぞれ設置されており、
浄化槽で浄化された排水が、側溝などの雨水へ放流されて
います(‘ω’)ノ

浄化槽はこんな感じのものが地中に埋まっています(‘ω’)


地中に埋まった浄化槽の放流側には、近くの側溝路と
接続します(‘ω’)

裏庭には里道が通っており、
その境界沿いに自分で排水路を設置しなおして、枡を設置(‘ω’)

そこに接続しています(‘ω’)
浄化槽から、この集水枡までの勾配はちゃんととれてますが、

洗面所、便所、、このあたりはあまり勾配がとれてません
でしたので、
当初から多分詰まりやすい想像はできてました(; ・`д・´)

こうして埋戻している状態ですと、配管の勾配なんて
わかりませんが、
工事中けっこう配管の様子をみていたので、緩い勾配だな、、
というのは確認していました(; ・`д・´)


浄化槽の天端もコンクリートで仕上げてもらい、
竣工時は綺麗にしていただきました(‘ω’)
毎年、三回の点検と、半年に一回、浄化槽内の清掃を
して管理しています(‘ω’)☆
その点検時に、汚れが酷かったり、配管の中に固形物など
溜まってきた場合は知らせてくれます(‘ω’)
洗濯機を回してたり、御トイレをジャーっと流したりすると、
室内にドブのような臭いがふわーっと気になるような時は、
雑排水管の中に固形物などが滞留していることが
考えられます(; ・`д・´)

汚水桝の蓋をあけて確認します(; ・`д・´)

この配管の底に溜まっている白いのが固形物です(; ・`д・´)
ドパーっと海の波のような水の流れがないと、
ねとねとの油汚れや、汚物は、こうして堆積
してしまいます(; ・`д・´)

とりあえず全部開けて、配管を洗浄していきたいと思います!

古い入線用スチールの先が折れたものを
配管内のホジホジ用のアイテムに代えてます(; ・`д・´)

そして高圧洗浄機もセッティング(; ・`д・´)

汚物だけでなく、風呂場では、トリートメントやリンス
などの粘度のあるものが流れるので、
そういったものもこびりついてしまうわけです(; ・`д・´)

2階からの合流した枡にもやはり汚れは堆積してますね(; ・`д・´)

浄化槽の蓋をあけます(‘ω’)ノ


小さな虫は湧いているものの、じつは、浄化槽の中は
そんなに臭いもひどいことはありません(; ・`д・´)

配管はすべて繋がっているため、臭い(空気の)逃げ場が
ないので、便所を流したり一気に排水した時などに、
封水が溶けて、配管内の臭いが排水口より室内に上がって
きます(; ・`д・´)
封水とは、
普段トイレの便器の中には水が溜まってますよね?
あれは配管内の臭いを水で蓋をしているということです(*’ω’*)
同時に虫などが排水口から配管内、浄化槽へと行き来できない
ように水でバリアーをしているわけです(; ・`д・´)

さて、それでは洗浄していきます(*’ω’*)

スチールでホジホジと固形物をとりながら奥へ押していき、、
水を流しながら、突き進んでいくと、、


汚れをおとしながら、スチールの先も出てきました(‘ω’)
これを繰り返して、汚れをこすりながら流して落とします(‘ω’)


やはりこすらないと、口元から高圧洗浄水をかけても
底にこびりついたものは落ちません(; ・`д・´)
高圧洗浄機の先に取付て、
配管内をずんずんとつきすすみながら高圧洗浄水を配管内で
噴射するタイプもあります(‘ω’)

我が家で一番ひどいのは、台所の排水から流れてきた
配管ですね(; ・`д・´)
カレーの残りや、油ものの洗い物をした時に十分流して
おかないと、どうしてもドロドロの雑排水は堆積していきます((+_+))


洗浄し終えると、底がきれいになっているのがわかります(‘ω’)


浄化槽のハンドホール縁の汚れもついでに洗浄(‘ω’)

配管内はきれいになって、
しばらくはこれで臭いもしないと思います(‘ω’)
お皿を洗うときや食べ残しを洗うときは排水に気を付ける
ようにしていますが、
1年に1回はじつは洗浄しています(; ・`д・´)
換気や空調の清掃もこまめに必要ですが、、
こうした雑排水や雨水の衛生設備の清掃もまたしっかりと
メンテナンスをすることが綺麗な家を保つ秘訣です(*’ω’*)