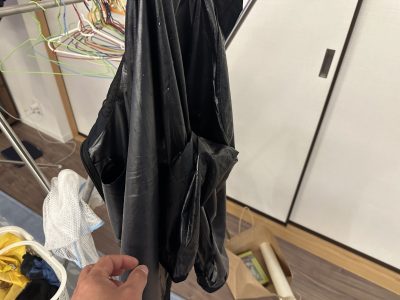はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!
作業着なんて、、いやされど作業着(; ・`д・´)
作業着こそ職人には大切な要素であり、
作業着や道具ひとつで、スキルの補助ができるかできないか
決まると言っても過言ではない(; ・`д・´)
バートル防水防寒着7620サブマリン①!

防寒着により体を保温できないと、手足を使う我々にとって
身体能力を十分発揮できませんが、
外仕事ですと、雨や雪が急に降ってきたりというコンディションも
もちろんでくわします(*’ω’*)

今回お試ししたのが、
バートルの防水防寒着7620という商品(*’ω’*)
通称【サブマリン】と言われており、撥水性能と透湿性能が
最強クラスということです(; ・`д・´)!

そのいかなるコンディションでも耐えうる一枚を発見しました!

この大型フード付きでヘルメットごとすっぽりと
寒さや雨風をしのげる、
いわば 【蒸れないカッパ兼防寒着】
なのである(; ・`д・´)!
バートルのストレッチフーディジャケット480!
↑インナーとして保温と防風目的に、フーディジャケットを
仕込ませるのも、いいのはいいのですが、
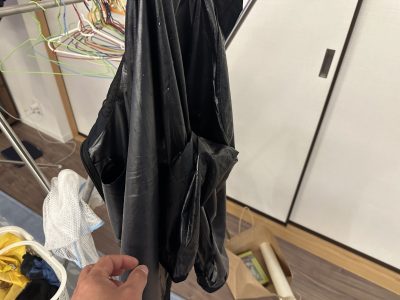
フーディジャケット480を洗濯すると、わかりますが、

脱水しても、裏生地に水分が残っているのが
わかります(; ・`д・´)
これは、着用してたら汗をかいても湿気が逃げない
ので、体内が温まって蒸気が発生しても
こういう状態が続いて、インナーや作業着がべしゃべしゃに
濡れてきたりして、
それが冷えて、風邪をひきやすくします(; ・`д・´)

防風系のパーカーなども過去いろいろ試しましたが、
伸長率があって伸びやすかったり、ゴワゴワしないものも
あるが、 その蒸れにくさ【透湿性】が乏しいものが
多い(; ・`д・´)
その前にまず、
【耐水圧性】 のお話(‘ω’)
耐水圧とは、生地に染み込もうとする水の力を抑える性能の
数値であり、 表面の撥水だけでなく、内部まで
しみ込んでこないかという基準である(‘ω’)
・300mm・・・小雨に耐えられる
・2,000mm・・・中雨に耐えられる
・10,000mm・・・大雨に耐えられる
・20,000mm・・・嵐に耐えられる
とある中で、
このサブマリン、耐水圧15,000mm と
ハイレベルがスペック(; ・`д・´)
ちなみにその辺で売ってるナイロンの傘は
250mm程度の耐水圧性能であるが、
一応ジャジャぶりの雨でも雨はしのげてますよね(; ・`д・´)
そう、次は雨はしのげるが、 蒸れるので
それをいかに蒸発させて通気をよくするかという話になる(‘ω’)

そこで【透湿性】
という言葉が出てくるが、
透湿性とは、
衣服内の水滴にならない蒸気状態の汗を生地が外に出す度合い
のことで、
24時間に何グラムの水分を外に出すのか、
ということを数値で表しています(‘ω’)
通常の防水防寒着だと5,000g/㎡/24hrs~10,000g/㎡/24hrs
くらいの数値のものが多いですが、
サブマリンはそれを上回る15,000g/㎡/24hrsです(‘ω’)
とても高機能な蒸れにくさを備えている(; ・`д・´)

機能的な数値は他のものよりハイスペックな
サブマリン
次回は着心地や感触をお伝えします(‘ω’)
、、次回へ続く(; ・`д・´)!